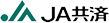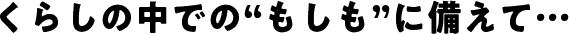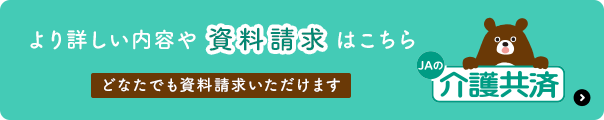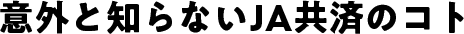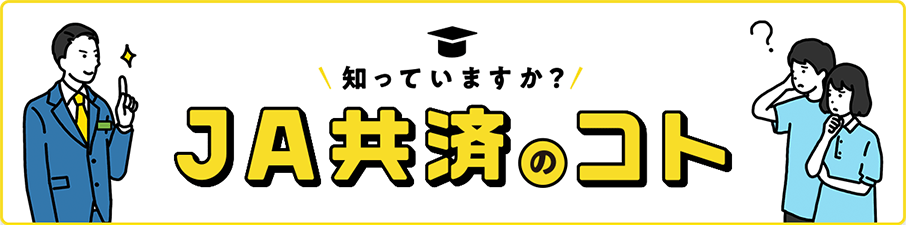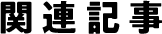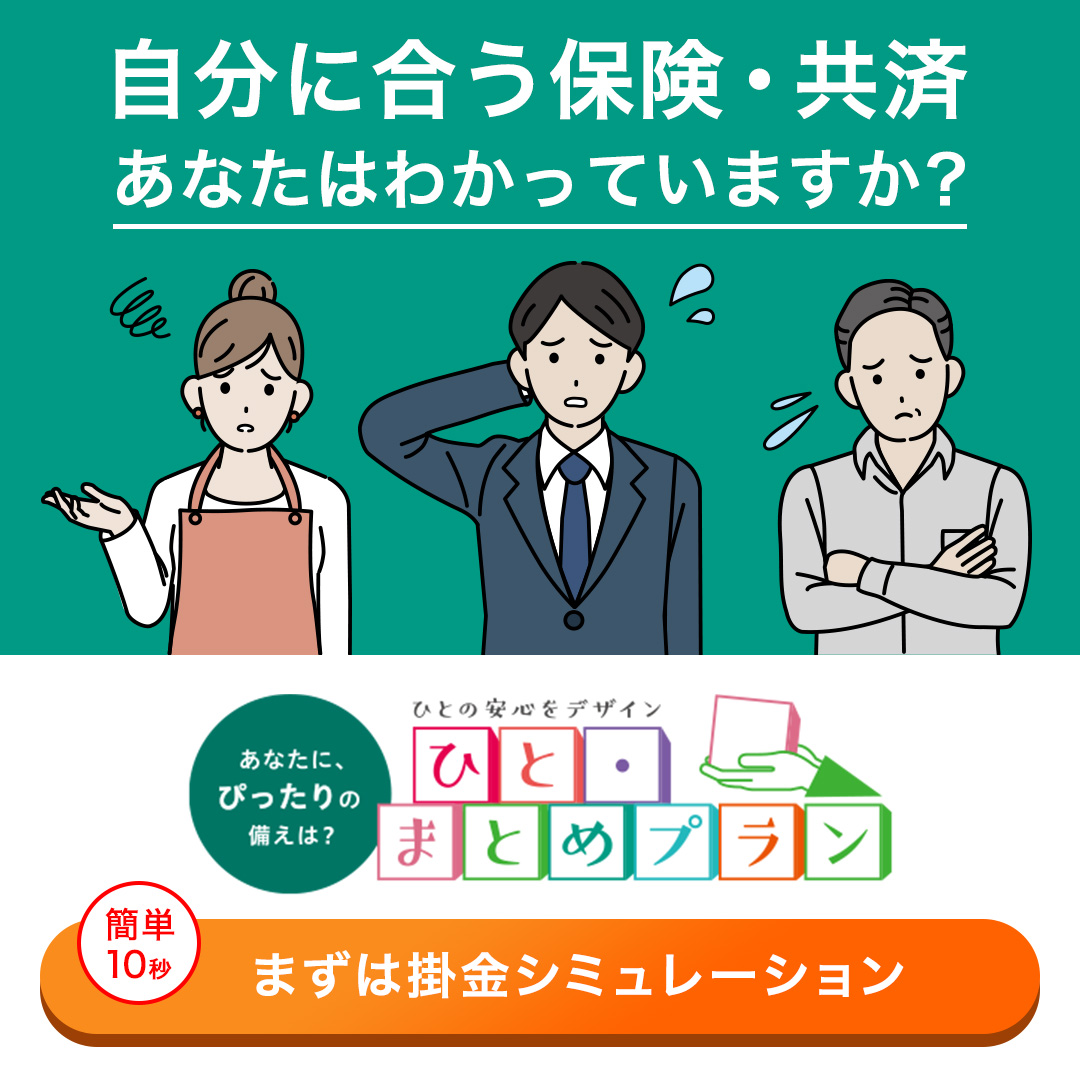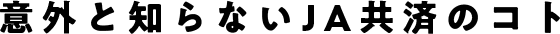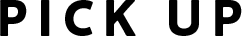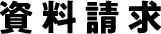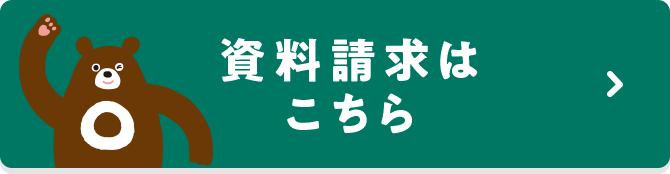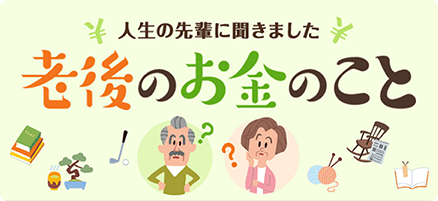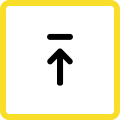訪問診療は公的介護保険・公的医療保険どちらが適用される?違いや自己負担額について
“老後”に関するねだんのこと
2024.12.23

訪問診療は、疾病や傷病などで通院が困難な場合に、自宅や介護施設などで診療を受けられる在宅医療の一種です。訪問診療を利用する予定のある方にとって、公的介護保険と公的医療保険のどちらが適用され、自己負担額がいくらになるかは気になるポイントといえます。
今回は、訪問診療で公的介護保険と公的医療保険のどちらが適用されるかや、自己負担額などを解説します。訪問診療の利用を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
本内容は、令和6年10月の制度等に基づき、記載しています。 本記事に記載の内容・条件は保険会社によって異なる場合がございます。詳しくは保険・共済各社・各団体へお問合せください。
見出し
訪問診療とは
訪問診療とは、通院が困難な患者さんの自宅や入所中の介護施設などに、医療従事者が定期的に訪問して提供する医療サービスのことです。一般的には、1週間ないし2週間に1回を目安に訪問し、患者さんの病状に合わせて以下のような対処をおこないます。
- 診療
- 治療
- 薬の処方
- 療養上の相談・指導
訪問診療と近いものに、「往診」があります。往診は、患者さんの体調が優れない場合に連絡を受けて、医療従事者が自宅や介護施設などを訪問して診療や治療をおこなうことです。
往診は、事前に訪問の予定が組み込まれておらず、突発的な体調の変化に対応します。一方訪問診療は、患者さんの状態を踏まえて計画的に訪問し、診療するという違いがあります。
公的介護保険と公的医療保険それぞれの概要と違い
ここでは、公的介護保険と公的医療保険の概要と違いについて解説します。
公的介護保険の概要
公的介護保険は、社会全体で介護を支えるため、2000年4月に創設された保険制度です。市区町村が保険者となり、制度を運営しています。
住民は40歳になると被保険者として公的介護保険への加入が義務付けられており、被保険者は、介護保険料を毎月支払わなければなりません。
厚生労働省の「介護保険サービスの対象者等」によると、40歳以上の方は公的介護保険の被保険者となり、年齢によって以下の2つの区分に分類されます。
- 第1号被保険者:65歳以上の方
- 第2号被保険者:40~64歳までの公的医療保険に加入している方
第1号被保険者は、要介護状態や要支援状態になった場合に、公的介護保険サービスを利用できます。一方、第2号被保険者が公的介護保険サービスを利用できるのは、初老期の認知症を始めとする指定の特定疾病によって、要介護状態や要支援状態になった場合に限定されています。
公的介護保険が適用された場合の利用者の負担額は、介護予防や介護器具の購入などの介護サービスに要した費用の1割(一定以上の所得者は2割または3割)です。例えば、1万円の介護サービスを利用した場合の自己負担額は、1,000円(一定以上の所得者は2,000円または3,000円)となります。
このように公的介護保険は、介護費用の自己負担額を軽減する効果があり、長期的に安心して介護を受けられる社会作りに役立っています。
関連記事:介護保険制度とは?対象となる疾病や受けられるサービスについて
医療保険(公的医療保険)の概要
医療保険(公的医療保険)は、病気や怪我をした場合に、医療費の一部を公的機関が負担する制度です。日本では「国民皆保険制度」を取り入れており、全国民に対して公的医療保険への加入が義務化されています。
公的医療保険は、以下の3つに分類されます。
- 被用者保険(健康保険・共済制度):会社員や公務員、その被扶養者が加入する
- 国民健康保険:自営業やその家族、学生、無職の方などが加入する
- 後期高齢者医療制度:75歳以上の方が加入する
公的医療保険に加入し、健康保険証を提示することで、医療費の自己負担額を1〜3割に抑えることが可能です。
また、公的医療保険には「高額療養費制度」も設けられています。高額療養費制度は、同一月にかかった医療費の自己負担額が高額となった場合に、自己負担限度額を超えた金額の払い戻しを受けられる制度です。
自己負担限度額は加入者の年齢や所得水準によって定められており、世帯で合算することもできます。
このように、公的医療保険には自己負担額を軽減する効果があるため、急な病気にかかった場合や、怪我をした場合でも、医療費が高額になる不安を抱かずに医療機関を利用できます。
関連記事:医療保険(共済)とは?昨今の医療保険制度や将来のために知っておきたい基礎知識を解説!
公的介護保険と公的医療保険の違い
公的介護保険と公的医療保険の違いをまとめると、以下のようになります。
| 公的介護保険 | 公的医療保険 | |
|---|---|---|
| 加入者 | 40歳以上 | 全国民 |
| 目的 | 加入者の介護費の負担を軽減する | 加入者の医療費の負担を軽減する |
| 適用条件 | 要介護または要支援の認定が必要 | 特になし |
| 公的介護保険 | 公的医療保険 | |
|---|---|---|
| 加入者 | 40歳以上 | 全国民 |
| 目的 | 加入者の介護費の負担を軽減する | 加入者の医療費の負担を軽減する |
| 適用条件 | 要介護または要支援の認定が必要 | 特になし |
公的介護保険は、介護費用の自己負担額を軽減する制度です。要介護者や要支援者が介護サービスを受けやすくするために創設されました。
一方、公的医療保険の目的は、病気や怪我による医療費の負担を抑えることです。これにより、日本では安心して医療サービスを受けられる環境が整えられています。
訪問診療には公的医療保険が適用される
訪問診療は、要介護認定の有無に関係なく、通院が困難な場合であれば受けられるサービスです。そのため、訪問診療は病院で診察や治療を受けた場合と同様に公的医療保険が適用され、かかった医療費の自己負担額を軽減できます。
具体的には、以下のような医療サービスに対して公的医療保険が適用され、医療費の負担軽減につながります。
- 在宅患者訪問診療料
- 在宅時医学総合管理料
- 各種指導管理料
- 検査
- 注射
- 投薬
- 診療情報提供書
訪問診療だけでなく、往診を利用した場合も公的医療保険が適用されるため、突如体調が悪化した際にも、自己負担額を抑えながら医療サービスを受けることが可能です。
訪問診療に公的介護保険が適用される場合もある
訪問診療では基本的に公的医療保険が適用されますが、その対象となるのは医療サービスに限定されます。
要介護認定や要支援認定を受けている方が医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士から療養上の管理や指導を受ける場合は、公的介護保険が適用されます。
職種ごとの療養上の管理や指導の具体例は、以下のとおりです。
| 指導者 | 指導内容 |
|---|---|
| 医師・歯科医師 | ケアプランの作成に必要な情報の提供、介護方法の指導 |
| 薬剤師 | 薬の飲み方の指導、処方どおりに薬を内服しているかの確認 |
| 管理栄養士 | 栄養管理に関する情報提供、献立や調理方法の指導 |
| 歯科衛生士 | 口腔内や入れ歯の清掃の指導、摂食・嚥下(えんげ)機能の指導 |
| 指導者 | 指導内容 |
|---|---|
| 医師・歯科医師 | ケアプランの作成に必要な情報の提供、介護方法の指導 |
| 薬剤師 | 薬の飲み方の指導、処方どおりに薬を内服しているかの確認 |
| 管理栄養士 | 栄養管理に関する情報提供、献立や調理方法の指導 |
| 歯科衛生士 | 口腔内や入れ歯の清掃の指導、摂食・嚥下(えんげ)機能の指導 |
療養上の管理や指導は、要介護者が対象の場合は「居宅療養管理指導」、要支援者が対象の場合は「介護予防居宅療養管理指導」と呼びます。公的介護保険の適用を受けるには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
- 居宅に月1回以上、訪問診療または往診を利用している
- 定期的にケアマネジャーへ診療情報提供をおこなっている
なお、要介護認定や要支援認定を受けていない方は、療養上の管理や指導を受けた場合でも、公的介護保険が適用されない点に注意しましょう。
訪問診療における公的医療保険の自己負担額
訪問診療においては医療サービスを受ける場合は、公的医療保険が適用されるため、医療費の自己負担額が軽減されます。
厚生労働省の「医療費の一部負担(自己負担)割合について」によると、公的医療保険における自己負担割合は年齢や所得によって異なり、区分ごとに負担する割合は以下のとおりです。
| 年齢 | 自己負担割合 |
|---|---|
| 75歳以上 |
|
| 70〜74歳 |
|
| 6〜69歳(義務教育就学後) | 3割負担 |
| 義務教育就学前 (6歳を迎える日以降の最初の3月31日まで) |
2割負担 |
| 年齢 | 自己負担割合 |
|---|---|
| 75歳以上 |
|
| 70〜74歳 |
|
| 6〜69歳(義務教育就学後) | 3割負担 |
| 義務教育就学前 (6歳を迎える日以降の最初の3月31日まで) |
2割負担 |
例えば、一般所得者等に該当する75歳の方の自己負担割合は1割であるため、月2回の訪問診療の費用が70,000円の場合の自己負担額は7,000円となります。75歳で現役並みの所得がある方の場合でも自己負担割合は3割であるため、21,000円の支払いで収まります。
このように、大幅に自己負担額が軽減されるため、訪問診療を利用する方にとって、公的医療保険が適用される恩恵は非常に大きいといえます。
一生涯にわたって備えるJA共済の介護共済
将来の介護費用について不安を感じている方は、公的介護保険にプラスして備えを充実させることも検討してみましょう。
なかでも利用しやすいのは、JA共済の介護共済です。加入対象となる年齢が40歳〜75歳と幅広いことに加え、一生涯にわたって備えられます。介護共済金を受け取れるのは、公的介護保険制度において要介護2〜5に認定されたタイミングと、所定の重度要介護状態になったときです。
介護共済金は一時金として一括で支給されるため、要介護や重度の介護状態になったときなど、まとまった支出が必要な場合でも役立ちます。「共済金年金支払特約」を付加し、所定の条件を満たしている場合は、介護共済金を年金形式で受け取ることも可能です。
詳しくは、お近くのJAにご相談いただくか、または、下記の「介護共済」のバナーからご確認ください。
参考・出典元:
厚生労働省 介護保険とは
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/about.html
厚生労働省 サービスにかかる利用料
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/fee.html
厚生労働省 我が国の医療保険について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken01/index.html
厚生労働省 医療費の一部負担(自己負担)割合について
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/dl/info02d-37.pdf