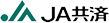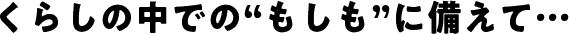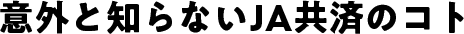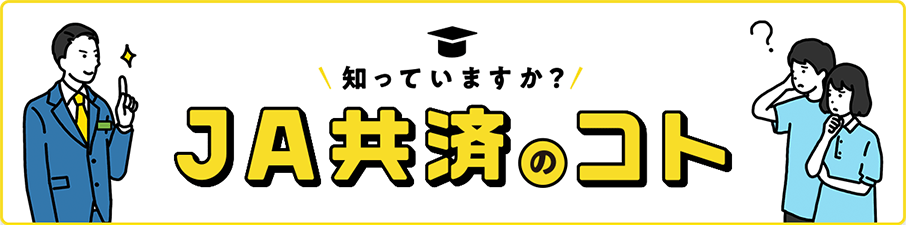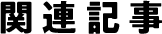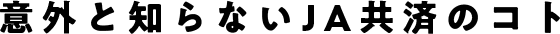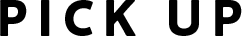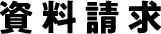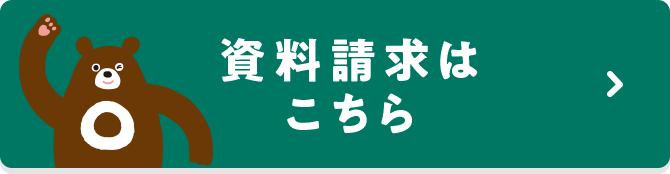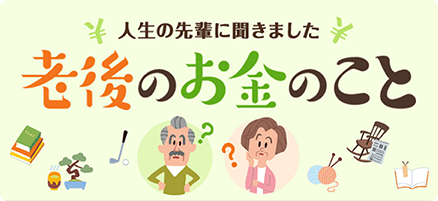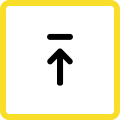出産手当金とは?申請方法や出産育児一時金との違いも解説
“子育て”に関するねだんのこと
2025.09.30
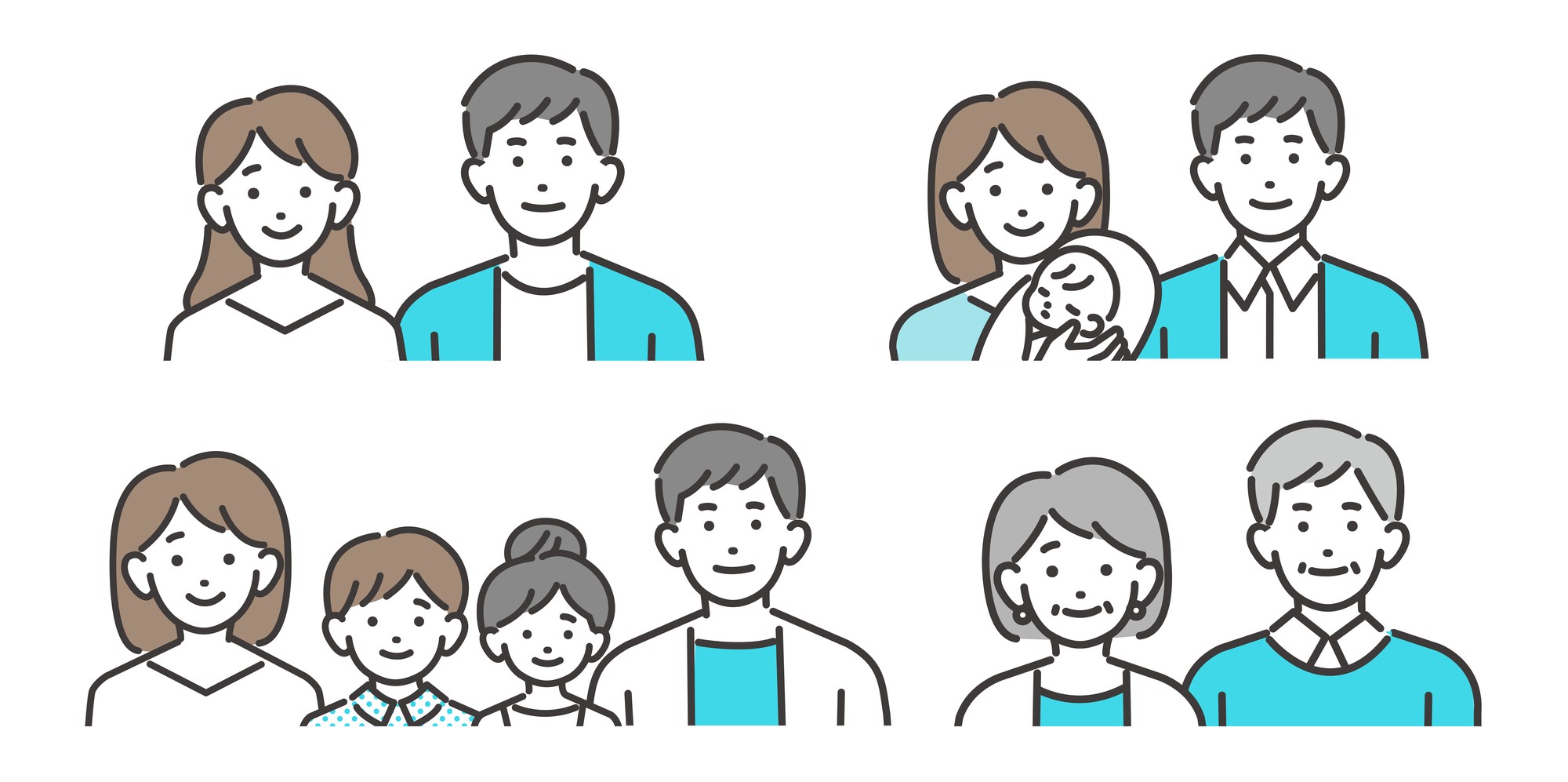
妊娠・出産を迎えるにあたって、不安要素の一つとなるのが収入面のサポートではないでしょうか。
こうした経済的な負担を軽減するために設けられている制度が「出産手当金」です。働く女性が出産前後に安心して休めるよう、一定期間の生活を支える役割を果たしています。
しかし、「誰が対象になるのか」「いくらもらえるのか」「どうやって申請するのか」など、詳しい内容がわからず不安に思う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、出産手当金の仕組みや支給額、申請の流れ、さらに混同しやすい出産育児一時金との違いについてもわかりやすく解説します。
これから妊娠を希望している方や出産を控えている方は、ぜひ参考にしてください。
本内容は、令和7年7月末の制度等に基づき、記載しています。本記事に記載の内容・条件によって異なる場合がございます。詳しくは、共済・保険各社・各団体へお問合せください。
見出し
出産手当金とは?
出産手当金とは、女性が出産のために会社を休み、その期間に給与の支払いがないなどの場合に、加入している健康保険から支給される手当です。
この制度は、会社の健康保険や公務員等の共済組合に加入している被保険者本人が対象となります。パートや契約社員であっても、勤務先の健康保険に加入していれば、出産手当金を受給できます。
出産前後は体調の変化も大きく、働くのが難しい時期です。その期間に収入が途絶えてしまうと、生活に大きな不安が生じます。出産手当金は、働く女性が安心して出産や休養に専念できるよう設けられた制度です。
出産育児一時金との違い
出産手当金と出産育児一時金は、どちらも出産に関連する公的な支援制度ですが、以下のようにそれぞれ目的が異なります。
| 名称 | 目的 |
|---|---|
| 出産手当金 | 被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにすること |
| 出産育児一時金 | 被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減すること |
出産手当金は、出産によって仕事を休まざるを得ない方の生活費を支援する制度であり、一定期間の収入を補うことを目的としています。一方で、出産育児一時金は、出産にかかる医療費や入院費用などを補助するもので、出産の際に発生する経済的負担を軽減する制度です。
なお、出産育児一時金は、健康保険に加入している被保険者本人だけでなく、その被扶養者が出産した場合にも支給されます。
この2つの制度は、それぞれ異なる側面から経済的負担を軽減し、安心して子どもを迎えられるよう支援する役割を担っています。
出産手当金はいくら支給される?計算方法も紹介
出産手当金として支給される1日あたりの金額は、「標準報酬日額」の3分の2に相当する額です。標準報酬日額とは、社会保険料の計算に使われる基準となる給与額(標準報酬月額)をもとに算出されます。
具体的な金額は、以下の計算式で求められます。
例えば、支給開始日以前12ヵ月間の標準報酬月額の平均が30万円だった場合、出産手当金の1日あたりの支給額は約6,667円となります。産前産後休業の期間が合計98日間であれば、支給総額は約65万円となる計算です。
ここで注意したいのは、「12ヵ月間の平均」とは、申請時点で任意に選べる期間ではなく、出産手当金の支給開始日以前の12ヵ月が対象となる点です。どの時期の給与が計算に使われるのか、事前に確認しておきましょう。
出産手当金の申請条件は?いつからいつまで支給される?
出産手当金を受け取るには、主に対象者や期間に関する要件を満たす必要があります。以下で詳しく説明しますので、ご自身が当てはまるか確認していきましょう。
申請条件
まず、出産手当金を受け取るには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 会社の健康保険や共済組合に加入している被保険者本人である
- 妊娠4ヵ月(妊娠85日)以降の出産である(早産や死産、流産の場合も対象)
- 出産のために仕事を休み、その期間に勤務先から給与が支払われていない
ただし、給与が支払われていても、その額が出産手当金の額より少なければ、出産手当金は支給されます。この場合の支給額は、出産手当金と給与の差額分になります。
申請期間
出産手当金の支給対象となる期間は、原則として、出産予定日以前42日間(多胎妊娠の場合は98日間)の産前休業と、出産の翌日から56日間の産後休業が対象となります。なお、出産当日は産前期間に含まれます。
具体的には以下の表をご覧ください。
<基本的な支給期間>
| 区分 | 支給期間 |
|---|---|
| 産前休業 | 出産予定日以前42日間 |
| 産後休業 | 出産の翌日以後56日間 |
| 合計 | 最大98日間 |
<多胎妊娠(双子以上)の場合の支給期間>
| 区分 | 支給期間 |
|---|---|
| 産前休業 | 出産予定日以前98日間 |
| 産後休業 | 出産の翌日以後56日間 |
| 合計 | 最大154日間 |
また、その期間に給与の支払いがないことも支給の条件となるため、あわせて確認しておきましょう。
出産手当金の申請方法
出産手当金を受け取るには、加入している健康保険への申請が必要です。手続きは大きく5つのステップに分かれており、それぞれに必要な記入や確認があります。
以下で順を追って申請の流れを解説しますので、スムーズな手続きのために全体像を把握しておきましょう。
①本人が出産手当支給申請書に記入する
まず、申請者本人が「健康保険出産手当金支給申請書」に必要事項を記入します。この書類は、出産手当金を受け取るための正式な申請書です。
申請書は勤務先から受け取るか、加入している健康保険の公式サイトからダウンロードできます。
氏名・住所・保険証の記号番号、振込先口座などの情報を正確に記入しましょう。記入できる箇所をあらかじめ埋めておくと、そのあとの手続きがスムーズになります。
②同じ書類を医師または助産師に記入してもらう
次に、出産した医療機関へ申請書を提出し、医師または助産師に「医師・助産師による証明」欄を記入してもらいます。出産日や子どもの人数など、出産の事実を証明する内容です。
この証明がなければ申請が受理されないため、忘れずに依頼しましょう。退院時に間に合うよう、余裕をもって依頼できると安心です。
③同じ書類を事業主に記入してもらう
本人と医師や助産師による記入が完了したら、記入済みの申請書を勤務先に提出し、「事業主が証明するところ」欄への記入を依頼します。ここでは、産休期間やその間の給与支払い状況などを記載してもらいます。
出産手当金は、産休中に会社から給与の支払いがない、または支払われた給与が出産手当金の額より少ない場合に支給されるため、事業主による証明が必要です。
人事や総務などの担当部署へ早めに相談しておきましょう。
④事業主が協会けんぽ・健康保険組合に提出する
必要事項の記入が完了したら、加入している健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に申請書を提出します。勤務先の担当部署を通じて提出される場合がほとんどのため、提出方法やタイミングについてあらかじめ確認しておくとよいでしょう。
提出が完了すると、出産手当金の申請手続きは完了です。
⑤出産手当金が指定口座に振り込まれる
提出された書類に不備がなければ、申請書に記載した本人の口座に出産手当金が振り込まれます。支給までの期間は、通常1〜2ヵ月程度です。
ただし、記入漏れや誤りがあると、確認に時間がかかり支給が遅れる場合があります。振り込みが確認できたら、一連の手続きは完了です。
出産後にかかるお金と教育資金の準備も考えよう
出産は、将来のお金のことを考えて計画的に準備を始めるのにちょうどよい機会です。出産手当金は産前産後の収入を一時的に補ってくれますが、子どもが生まれてからも子育てにはお金がかかり続けます。
特に教育費については、子どもの成長にともない、その負担は徐々に増していく一方です。文部科学省および独立行政法人日本学生支援機構の調査によると、子ども1人が大学を卒業するまでにかかる教育費は、すべて国公立に進学した場合でも800万円以上といわれています。
こうした将来の出費に備えるためには、早いうちから準備を始めておくと安心です。
JA共済の「こども共済」には、以下の以下の4つの特長があります。
特長①学資金のお受取りは、進学時期に合わせた中学・高校・大学プランからお選びいただけます。
特長②高い貯蓄性と保障がバランスよく備わっていて、効率的に資金準備できます。
特長③ご契約者(親族)がもしものとき(※1)、その後の共済掛金はいただきません(※2)。
特長④お子さま・お孫さまのために75歳までご契約いただけます(※3)。
出産後、新たにかかる教育費を計画的に備えていく方法の一つとして、学資保険を検討してみてはいかがでしょうか。
(※1)「もしものとき」とは、死亡、所定の第1級後遺障害の状態、所定の重度要介護状態または災害による所定の第2級~第4級の後遺障害の状態になられたときをいいます。
(※2)共済掛金払込免除不担保特則を付加する場合を除きます。
(※3)ご契約者の年齢や健康状態に関わらずご契約いただけるプランもございます(共済掛金払込免除不担保特則を付加する場合に限ります)。
参考・出典元:
厚生労働省 母性健康管理に関する用語辞典
https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/glossary/provide02.html
厚生労働省 保健局 出産育児一時金について
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001000562.pdf
全国健康保険協会 協会けんぽ 子供が生まれたとき
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3280/r145/
文部科学省 令和5年度子供の学習費調査
https://www.mext.go.jp/content/20241225-mxt_chousa01_000039333_3.pdf
独立行政法人日本学生支援機構 令和4年度学生生活調査結果
https://www.jasso.go.jp/statistics/gakusei_chosa/__icsFiles/afieldfile/2024/03/25/data22_all.pdf