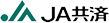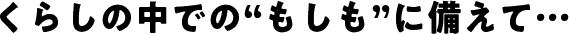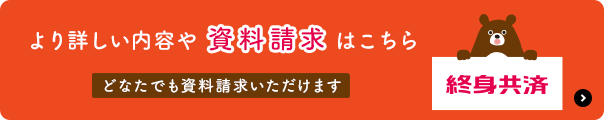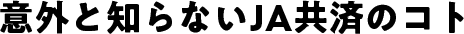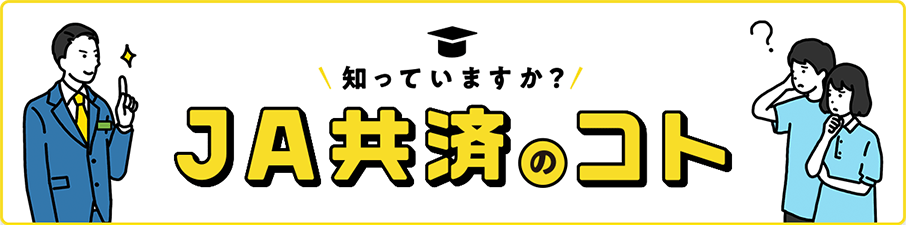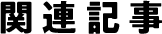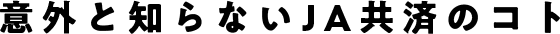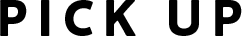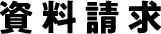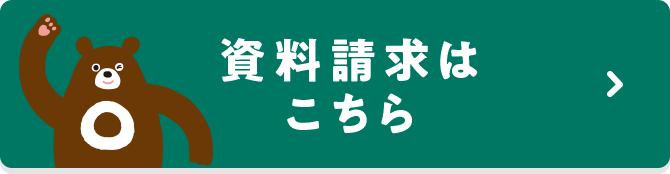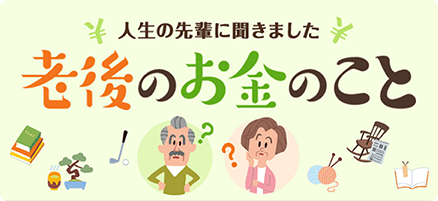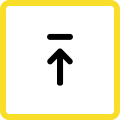葬儀費用の相場はどのくらい?負担を抑える方法も解説
“家族”に関するねだんのこと
2025.03.31
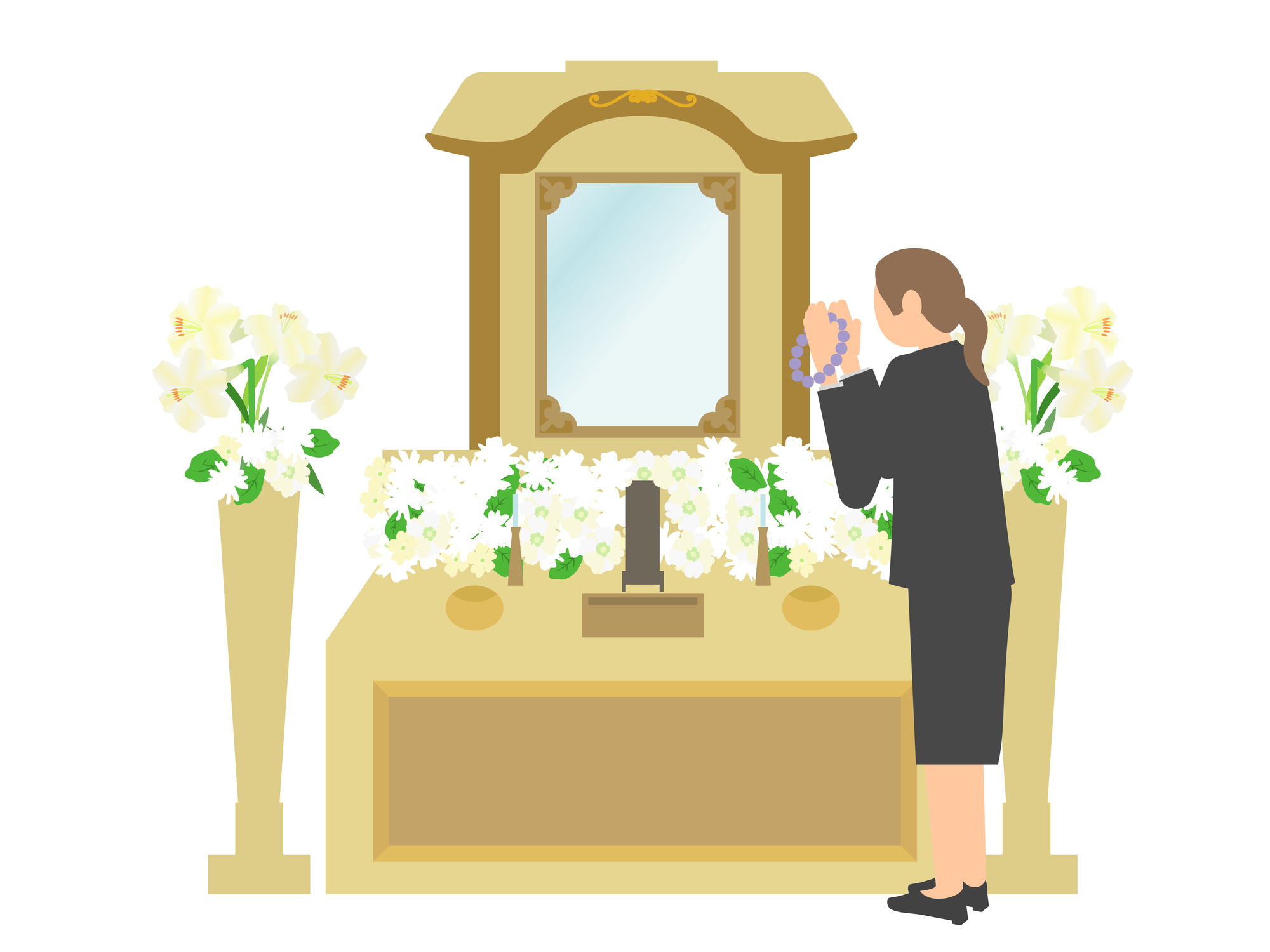
葬儀費用は、一般葬や家族葬などの形式や、依頼する葬儀会社によって大きく異なります。安心して葬儀の準備をするためにも、事前にどのくらいの費用が必要かを把握しておきたい方も多いことでしょう。
今回は、葬儀費用の相場や、形式ごとの平均費用、葬儀費用を抑える方法などを詳しく解説します。葬儀費用の相場を理解し、必要な資金を準備したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
本内容は、令和7年1月の制度等に基づき、記載しています。 本記事に記載の内容・条件は保険会社によって異なる場合がございます。詳しくは保険・共済各社・各団体へお問合せください。
葬儀費用の相場はどのくらい?
株式会社鎌倉新書が2024年3月に実施した「第6回お葬式に関する全国調査(2024)」によると、葬儀費用の総額の全国平均は118.5万円です。
この金額には、「基本料金」「飲食費」「返礼品費」が含まれています。ここでは、それぞれの費用の相場を詳しく見ていきましょう。
基本料金
基本料金とは、葬儀をおこなうための基本的な費用を指し、主に以下の費用が含まれています。
- 斎場利用料
- 火葬場利用料
- 祭壇
- 棺
- 遺影
- 搬送費
基本料金の平均は75.7万円であり、葬儀費用の総額の約6割を占めています。
飲食費
飲食費は、通夜後や火葬後に弔問客に提供する料理(通夜ぶるまい、精進落とし)などにかかる費用です。葬儀の飲食費の平均は20.7万円ですが、会食のグレードや参列人数によって金額は大きく変わります。
返礼品費
返礼品費とは、香典返しにかかる費用です。返礼品費の平均は22.0万円ですが、飲食費と同様に葬儀の参列人数に比例して増減します。
形式別の葬儀費用の平均相場
葬儀費用の全国平均は118.5万円とお伝えしましたが、葬儀形式の違いによって費用の相場は大きく異なります。
ここでは、株式会社鎌倉新書の調査結果をもとに、葬儀形式ごとに葬儀費用の平均相場を紹介します。
一般葬
一般葬とは、参列者を家族や親族だけに限定せず、故人と関わりのあった幅広い方が参列する葬儀形式で、葬儀費用の平均総額は161.3万円です。
一般葬では、基本的に通夜や告別式を2日に分けておこない、参列人数が多い傾向があります。斎場の利用料や飲食費、返礼品費の負担も大きくなるため、もっとも費用がかかる葬儀形式です。
家族葬
家族葬とは、家族や親戚、親しい方を中心に故人をお見送りする葬儀形式で、葬儀費用の平均総額は105.7万円です。通常、通夜と告別式を2日に分けておこないますが、参列者が多くないため、一般葬と比べて小さめの会場で実施されることが多いのが特徴です。
また、必要な料理や返礼も少なくなるため、一般葬と比べると費用が安く済む傾向があります。家族葬では、会食の席を設けない場合もあり、飲食費の負担を大幅に軽減することも可能です。
一日葬
一日葬とは、通夜を省き、葬儀・告別式・火葬を1日で執りおこなう葬儀形式で、葬儀費用の平均総額は87.5万円です。
1日で葬儀をおこなうことにより、会場の利用料を抑えられます。また、一般葬と比べると参列者が少なくなる傾向があり、飲食費や返礼品費も軽減できます。
直葬・火葬式
直葬・火葬式とは、遺体を安置施設へ搬送後、通夜・葬儀・告別式を実施せずに火葬のみで送る葬儀形式で、葬儀費用の平均総額は42.8万円です。
棺代や遺体の搬送費、火葬料などは必要ですが、葬儀会場が不要なため、費用をもっとも安く抑えられます。
葬儀費用の負担を抑える方法
葬儀費用はまとまった金額が必要になるため、できる限り抑えたいと考えている方も少なくないでしょう。ここでは、葬儀費用の負担を抑える6つの方法を紹介するので、ぜひ参考にしてください。
相見積もりを取る
葬儀費用は葬儀会社によって金額が異なるため、相見積もりを取ることで、費用を安く抑えられる葬儀会社を選べます。
ただし、費用の安さだけで葬儀会社を選ぶと、必要なサービスが含まれない場合があります。故人や家族が希望する葬儀を実現できるか確認してから、依頼先を決めましょう。
小規模な葬儀形式を選ぶ
前述したように、葬儀ごとに葬儀費用は大幅に変動するため、小規模な葬儀形式を選ぶことで金銭的負担を抑えられます。
特に、一般葬にかかる葬儀費用の平均総額は161.3万円と高額です。そのため、葬儀費用を抑えたい場合は、故人の希望を尊重しながらも、他の3つの形式を検討するとよいでしょう。
ただし、一般的に葬儀が小規模になるほど香典も少なくなるため、実質負担額が増える可能性がある点には注意が必要です。葬儀費用だけでなく、予想される参列者数を考慮したうえで、故人と家族にとって最適な形式を選びましょう。
補助・扶助制度を活用する
葬儀費用を少しでも安く抑えたい場合、補助・扶助制度の活用が効果的です。例えば、加入している公的医療保険によって、以下のような給付を受けられます。
| 保険の種類 | 給付内容 | 支給対象者 |
|---|---|---|
| 健康保険 |
|
|
| 共済保険 |
|
|
| 国民健康保険 | 被保険者の死亡時に、自治体ごとに定められた葬祭費を支給 | 被保険者の葬祭をおこなった方 |
※被扶養者以外が請求する場合は実際に埋葬に要した費用(上限5万円)
この他にも、生活保護世帯の方が亡くなった場合は、葬祭扶助として埋葬費が支給されます。
このような制度を活用して葬儀費用の一部を賄うことで、金銭的な負担を抑えられます。ただし、いずれの制度を利用する場合でも申請が必要なため、給付金を受け取りたい方は忘れずに手続きしましょう。
僧侶手配(派遣)サービスを利用する
あまり知られていませんが、僧侶手配(派遣)サービスを利用することで葬儀費用を安く抑えられる可能性があります。
僧侶手配とは、通夜や葬式、四十九日などの法事・法要に僧侶を紹介、派遣してくれるサービスです。
先祖代々の葬儀を執りおこなってきた寺(菩提寺)の住職に依頼すると、お布施が高額になる場合があります。一方で、僧侶手配ではサービス利用料にお布施も含まれているため、費用が明確で、全体の費用を抑えやすい点がメリットです。
このようなサービスは、僧侶派遣専門の会社や団体、宗教法人などから依頼できます。各Webサイトに、お布施料金や戒名料など必要な費用の目安が記載されているため、気になる方は一度確認してみてください。
香典を支払いに充てる
参列者からいただいた香典を葬儀費用の支払いに充てることで、自己負担額を抑えることもできます。
香典を葬儀費用に使ってもよいのか不安な方もいるでしょうが、香典は喪主のものと考えるのが一般的です。香典には故人の霊前に供えるだけでなく、遺族の葬儀費用の負担を軽くする目的もあるため、葬儀代に充てても構いません。
ただし、特に一般葬以外では香典の総額が少なくなる傾向があるため、必ずしも香典で葬儀費用をすべて賄えるわけではないという認識を持っておきましょう。
葬儀費用に関して事前に確認すべきポイント
ここでは、葬儀費用に関して事前に確認すべき4つのポイントを紹介します。
遺言書で葬儀に関する指定がないか
故人が遺言書で葬儀に関する指定をしているかどうかは、事前に確認すべき重要なポイントです。
遺言書に葬儀に関する内容が記載されている場合、可能な限り故人の遺志にしたがって葬儀を進めたほうが後悔が少ないでしょう。
故人が葬儀会社と生前契約を結んでいたか
故人が葬儀会社と葬儀の生前契約を結んでいたかどうかも、事前に確認しておきたいポイントです。
葬儀を依頼する前に、家族の誰かが故人から生前契約について聞いていないか、また遺言書に関連する記載がないかを確認しましょう。
生前契約を結んでいれば、すでに葬儀費用を葬儀会社に支払っている場合があり、経済的負担を軽減できる可能性があります。
故人が生命保険などに加入していたか
故人が生命保険などに加入していた場合、死亡保険(共済)金を受け取れる可能性があります。
まずは保険証券を探したり、故人の通帳から生命保険料の引き落とし履歴を確認したりして、保険(共済)の加入状況を調べましょう。
葬儀費用を誰が負担するか
葬儀費用は、基本的には喪主が負担します。喪主は、故人の配偶者や血縁関係のある実子が務めることが多いですが、誰が喪主を務め、葬儀費用を負担するかは法律で定められているわけではありません。
そのため、誰が葬儀費用を負担するかを巡って、金銭トラブルが発生する可能性があります。遺族同士の揉めごとを避けるためにも、葬儀会社と契約する前に事前協議をおこなうことをおすすめします。
JA共済の終身共済は一生涯の万一保障が可能!
自分が亡くなったあと、家族に葬儀費用の負担をかけるのが心配な方は、JA共済の終身共済を利用する方法があります。
終身共済に加入しておくと、その方の生死などに関して共済金等が支払われることとなる方(被共済者)が万一(死亡など)の場合、死亡共済金が支払われるため、遺族の経済的負担を軽くできます。
終身保障を検討している方は、一生涯にわたって万一の保障を確保できる「終身共済」がおすすめです。
「終身共済」では、万一(死亡など)の場合に遺族が共済金を受け取ることができ、その後の生活費や葬儀費用などに充てられます。家族への負担を少しでも軽くしたいとお考えの方は、ぜひ「終身共済」のご利用をご検討ください。
参考・出典元:
株式会社鎌倉新書 第6回お葬式に関する全国調査
https://www.e-sogi.com/guide/55135/
全国健康保健協会 ご本人・ご家族が亡くなったとき
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3200/r149/
日本郵政共済組合 埋葬料・家族埋葬料
https://www.yuseikyosai.or.jp/tanki/maiso.html
東京都保健医療局 身寄りのない方が亡くなられた場合の遺留金等の取扱いの手引
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/kokuho/aramashi/kyuufu/kyuufu08
内閣府ホームページ 葬祭扶助
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/doc/tb_r1fu_12mhlw_85_87b_2.pdf
国税庁 No.4129 相続財産から控除できる葬式費用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm
e-Gov法令検索 民法 第千五条
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
政府広報オンライン 家族の生命保険契約を一括照会!どこの会社に加入しているか調べられます
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202111/2.html
一般社団法人全国銀行協会 遺産分割前の相続預金の払戻し制度のご案内チラシ
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/article/F/7705_heritage_leaf.pdf