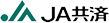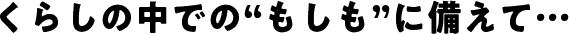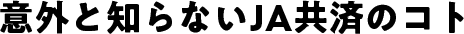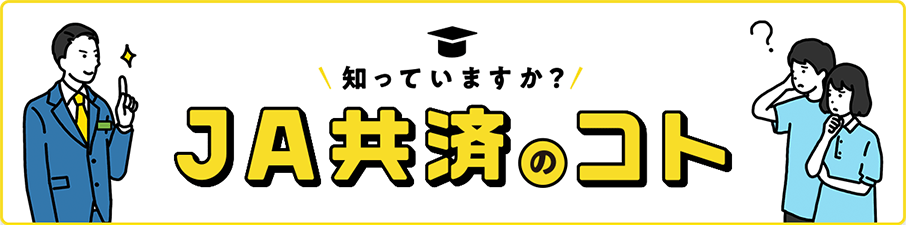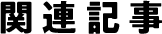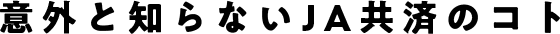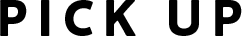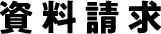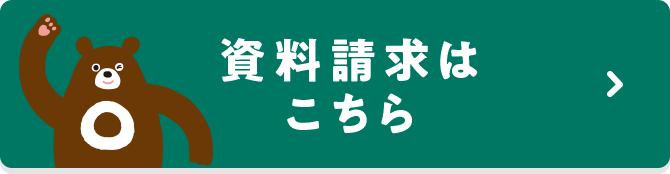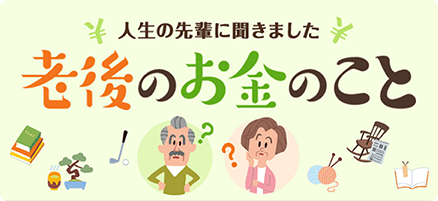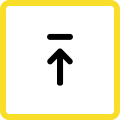自動車保険の等級引継ぎは可能?家族・乗り換え・中断証明の条件も解説
“家と車”に関するねだんのこと
2025.09.30

自動車保険は、一定の条件を満たせば等級引継ぎが可能です。無事故の実績を引継ぐことで新しい契約先での保険料(掛金)が軽減できるため、長期的な節約につながります。
なお等級は、車を買い替えるのか名義を変更するのかなど、条件により引継ぎ方法や必要書類が異なります。等級引継ぎのタイミングと合わせて把握しておくと、経済的リスクを回避できるでしょう。
今回は、自動車保険の等級引継ぎに求められる条件や、引継ぎ方法・最適なタイミングなどを解説します。自動車保険の等級引継ぎの仕組みを詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
本内容は、令和7年7月末の制度等に基づき、記載しています。本記事に記載の内容・条件によって異なる場合がございます。詳しくは、共済・保険各社・各団体へお問合せください。
見出し
自動車保険の等級制度とは?
自動車保険では、契約者の事故歴に応じて「等級」が設定されます。等級とは、保険料(掛金)の割増引に関係する大切な数値です。
ここでは、自動車保険の等級の基本事項や保険料(掛金)への影響を詳しく解説します。
等級の基本
自動車保険の等級は1等級から20等級まであり、等級が上がるほど保険料(掛金)の割引率が高くなるのが一般的です(ノンフリート等級別料率制度)。「無事故」と「事故有」の区分に応じて、異なる割増引率が適用されます。
初めて自動車保険に加入した場合は、原則6等級からのスタートです。1年間無事故で保険(共済)を利用しなければ、一般的に更新の際、7等級へ上がります。
自動車保険における等級による保険料の割増引率
等級による保険料(掛金)の割増引率は、以下の表のとおりです。
| 等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無事故 | 108% | 63% | 38% | 7% | −2% | −13% | −27% | −38% | −44% | −46% |
| 有事故 | −14% | −15% | −18% | −19% |
| 等級 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無事故 | −48% | −50% | −51% | −52% | −53% | −54% | −55% | −56% | −57% | −63% |
| 有事故 | −20% | −22% | −24% | −25% | −28% | −32% | −44% | −46% | −50% | −51% |
※一般社団法人 日本損害保険協会「問23 自動車保険の「等級」について教えてください。」より引用
例えば、12等級で無事故の場合の割引率は−50%、有事故では−22%となっており、同じ等級でも事故の有無によって大きな差が生じることが分かります。
また、12等級時に事故を起こすと3等級下の9等級にランクダウンします。保険料は−18%にとどまり、割引率が大きく下がることが読み取れるでしょう。
自動車保険の等級引継ぎは可能?
自動車保険は、一定の条件を満たせば等級を引継げる可能性があります。自動車保険で等級を引継げる場合と引継げない場合の条件について、詳しく説明します。
等級が引継げる場合
自動車保険の等級は、同じ契約者で車を買い替えたり名義を変更したりするケースなどでは、引継ぎが可能です。積み重ねた無事故の実績を上手に活用し、保険料(掛金)の節約につなげましょう。
ここでは、等級が引継げる代表的な4つのケースを紹介します。
車の買い替え(同じ契約者)
車を買い替える際に、契約が引継ぎ可能な用途車種であれば、自動車保険の等級は新しい車に引継げます。重要なのは、契約者が同一であることです。
新車の納車日が分かれば事前に等級引継ぎの手続きを済ませられるため、早めに保険会社へ連絡しましょう。
保険会社の乗り換え(契約者=被保険者)
前契約の保険会社で「ノンフリート等級別料率制度」が適用されていた場合は、自動車保険を他社に乗り換えても等級は引継がれます。
自動車保険の等級や事故歴に関する情報は、各保険会社間で共有されるため、契約者と被保険者が同一であれば保険会社を乗り換えても等級が維持される仕組みです。
家族間での名義変更
家族間で車を譲り渡す場合も、一定の条件を満たせば自動車保険の等級を引継げます。なお、引継ぎが認められるのは、以下のいずれかの関係性に限られます。
- 配偶者
- 同居の親族
- 配偶者と同居の親族
※配属者には、内縁、同性パートナーが含まれる場合があります。
例えば、契約者=被保険者の父親から車を譲り受けた子ども(契約者=被保険者の場合)が「同居している親族」であれば、等級引継ぎが可能です。運転免許を取得して間もない方は、一般的に6等級からのスタートになりますが、父親の等級を反映すれば保険料(掛金)の負担を軽減できるでしょう。
中断証明書を利用して再開する場合
契約者が自動車保険の契約を一時中断しても、「中断証明書」があれば以前の等級からスタートできます。
「中断証明書」とは、自動車保険を解約または満期後に継続しない場合に発行できる証明書で、発行には自動車の廃車等の条件が必要です。証明書には、中断前の等級や事故履歴などが記載されています。
自動車保険を再契約する際、事前に中断証明書を提出しており、中断から10年以内かつ一定の条件を満たしていれば、過去の等級が適用されます。
そのため廃車や譲渡、駐在・留学などで車を手放す予定の方は、将来の再契約に備えて中断証明書を取得しておくのがおすすめです。なお、保険会社により中断証明書の発行条件は異なるため注意しましょう。
自動車保険の等級引継ぎの手続き方法
自動車保険の等級引継ぎの手続きは、ケースによって方法が異なるため注意が必要です。ここでは、等級引継ぎでよくある3つの手続き方法を詳しく紹介します。
車を買い替える場合
車の買い替えで旧車の等級を新車に引継ぎたい場合は、「車両入替の手続き」をしましょう。車両入替の手続きは、以下の手順で進めます。
- 新車の車検証や場合によっては、積算走行距離計(オドメーター)の数値を用意する
- 変更手続きをする
新車の納車前で車検証がない場合は、以下の情報を用意します。
- 車種
- 型式
- 車両番号または登録番号(ナンバープレート)
- 車台番号
- 初度登録年月または初度検査年月
- 車両所有者情報
保険会社を乗り換える場合
他社の自動車保険に乗り換える場合は、新しい保険会社への加入手続きが必要です。保険会社の加入手続きは、以下の手順で進めます。
- 運転免許証・車検証・加入中の自動車保険の保険証券を用意する
- 変更手続き(契約の終期日から他社の契約に乗り換えるように手続きする場合や今の契約を解約して、同日から他社で契約するように手続きする場合など)をする
また、前契約の解約から時間が経過している場合は、中断証明書を提示しましょう。
車の名義を変更する場合
配偶者や同居の親族から車を譲り受け自動車保険の等級を引継ぐ際は、「記名被保険者の名義変更手続き」が必要です。
自動車保険には「契約者・記名被保険者・車両所有者」の3つの名義が存在します。主たる運転者が変わる場合は、必ず記名被保険者の変更手続きをしましょう。
記名被保険者の変更手続きの手順は、主に以下のとおりです。
- 電話で保険会社に車の名義変更を申し出る
- 保険会社が送付する「変更届出書」に必要事項を記入する
- 保険会社に「変更届出書」と運転免許証の写しを提出する
新しい記名被保険者の年齢・保障内容・用途車種等によっては、追加の保険料(掛金)が発生するケースがあります。
自動車保険の等級引継ぎはいつする?
自動車保険の等級引継ぎは、「満期日(終期日)、または満期日(終期日)の翌日から起算して7日以内」におこないましょう。この期間を過ぎると基本的に等級は引継げず、新規契約扱いとなります。
自動車保険の解約から新しい自動車保険への乗り換えの際、8日以上期間が空く場合は「中断証明書」を発行しましょう。
引継ぎで損しないために自動車保険の等級を理解しておこう
自動車保険の等級制度を正しく理解すれば、保険料(掛金)を抑えられます。 車の乗り換えや自動車保険の中断を予定している場合は、中断証明書の発行や等級引継ぎの手続きを申請し、等級の実績を上手に活用しましょう。
カーライフへの備えを充実させたい方は、車や運転者の損害を保障する保険(共済)への加入を検討しましょう。
JA共済の「自動車共済 クルマスター」は、車の事故による賠償やケガ・修理への備えを保障する共済です。24時間・365日の事故受付や手厚い保障サービスで、カーライフの安心と充実をご提供します。
車の損害に備えたい方は、JA共済の「自動車共済 クルマスター」への加入をご検討ください。
参考・出典元:
一般社団法人 日本損害保険協会 【自動車保険】ノンフリート等級別料率制度が改定されます
https://www.sonpo.or.jp/insurance/car/bs9fm9000000016o-att/nonfreet.pdf
一般社団法人 日本損害保険協会 くるまの保険/任意の自動車保険
https://soudanguide.sonpo.or.jp/car/q023.html
損害保険料率算出機構 2024年度自動車保険の概況
https://www.giroj.or.jp/publication/outline_j/j_2024.pdf#view=fitV