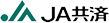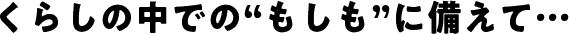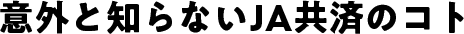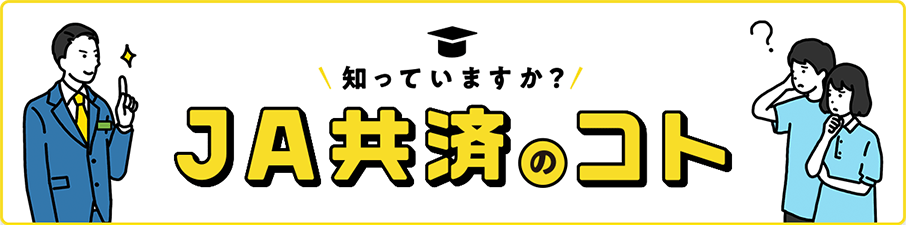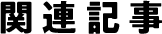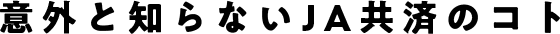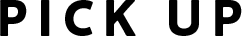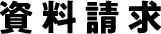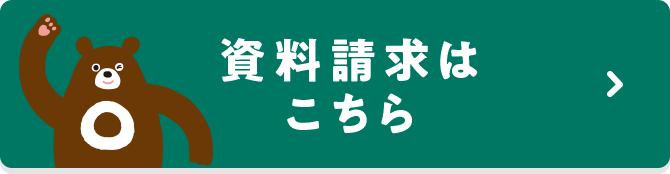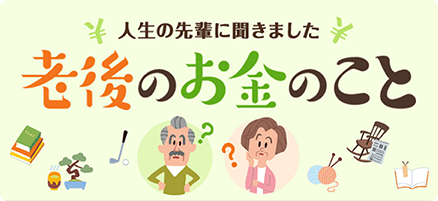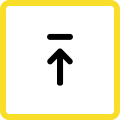固定資産税の計算方法!シミュレーション例や支払い方法を解説
“就労”に関するねだんのこと
2025.09.30

固定資産税は、土地や家屋などの不動産を所有している場合に毎年課される地方税です。評価額によって税額が大きく変わるため、その根拠に疑問を持つ方も多いでしょう。
固定資産税の計算方法を知っておけば、おおまかな金額を把握でき、納税額に対する不安を解消できます。また、税額を抑えられる特例措置や支払い方法をあらかじめ確認しておけば、毎年の支払いに備えられるでしょう。
今回は、固定資産税の計算方法や実際のシミュレーション・支払い方法を解説します。固定資産税の仕組みや支払い方法を詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
本内容は、令和7年7月末の制度等に基づき、記載しています。本記事に記載の内容・条件によって異なる場合がございます。詳しくは、固定資産税通知元の団体へお問合せください。
見出し
固定資産税は自分でも計算可能
固定資産税の通知は、毎年4月~5月頃に届きます。通知が来る前に固定資産税を計算しておき、納税の準備を万全に整えておきましょう。
なお、固定資産税は不動産を所有している場合に、毎年地方自治体に納めなくてはいけない税金の一つです。税額は評価額や用途に基づき算出されるため、仕組みを理解すれば、事前におおよその金額を把握できます。
固定資産税の計算方法
固定資産税の計算式は、以下のとおりです。
税額=課税標準額 ×標準税率(1.4%)
税率は原則1.4%と定められていますが、各自治体では必要に応じて、1.4%と異なる税率を条例で定めることができます。事前に居住地の市町村情報を確認しておきましょう。
また、課税標準額は「固定資産の評価額」をもとに算出します。固定資産の評価は、土地や家屋・償却資産ごとに計算されるのが特徴です。
土地・家屋の場合
土地・家屋の評価額の計算式は、以下のとおりです。
評価額=土地や家屋の課税標準額×標準税率(1.4%)
さらに土地や家屋の課税標準額は、以下の内容などにより計算されます。
- 土地:公示価格の70%程度
- 家屋:請負工事金額の60%程度
固定資産評価額基準に基づいて各自治体が決定され、3年ごとに「評価替え」が実施されます。
償却資産の場合
償却資産の評価額の計算式は、以下のとおりです。
評価額 = 取得価額× 減価残存率
毎年1月1日時点での評価額の合計が課税標準額となります。前年中に取得したか、前年前に取得したかで評価方法が異なるため注意しましょう。
固定資産税のシミュレーション
固定資産税は、不動産の条件によって金額が大きく変動します。シミュレーションを用いて、各条件ごとにかかる固定資産税を算出してみましょう。
新築一戸建て
4,500万円の新築一戸建てを、以下の条件でシミュレーションした場合の計算方法です。
【条件】
- 新築の認定長期優良住宅
- 土地の購入価格:2,000万円
- 家屋の請負工事金額:2,500万円
- 土地面積:150㎡
- 税率:1.4%
固定資産税評価額
- 土地:2,000万円×70%=1,400万円
- 家屋:2,500万円×60%=1,500万円
小規模住宅用地の特例と新築住宅特例措置が適用された場合、以下の計算をします。
※特例措置については、のちほど詳しく説明します。
固定資産税
- 土地:1,400万円(固定資産税評価額)×1/6(小規模住宅用地の特例)×1.4%=約3.3万円
- 家屋:1,500万円(固定資産税評価額)×1/2(新築住宅特例措置)×1.4%=10.5万円
固定資産税額は、約3.3万円(土地)+10.5万円(家屋)=約13.8万円です。
中古マンション
築10年・3,000万円で購入した中古マンションを、以下の条件でシミュレーションした場合の計算方法です。
【条件】
- 築10年の中古マンション
- 新築時の固定資産評価額:3,000万円
- 家屋:専用面積100㎡、3階建て以上耐火構造住宅
- 土地面積:100㎡
- 税率:1.4%
固定資産税評価額
3,000万円×70%=2,100万円
土地を600万円、家屋を1,500万円とし、固定資産税を計算します。
固定資産税
- 土地:600万円(固定資産税評価額)×1/6(小規模住宅用地の特例)×1.4%=1.4万円
- 家屋:1,500万円(固定資産税評価額)×1.4%=21万円
固定資産税額は、1.4万円(土地)+21万円(家屋)=22.4万円です。
家屋は、経年劣化ごとに「経年減価補正率」を乗じます。そのため、経過年数に応じて固定資産税は減っていきます。
固定資産税の支払い方法
固定資産税の支払い方法には、いくつかの選択肢があります。ご自身のライフスタイルに合わせて、最適な支払い方法を選びましょう。
ここでは、代表的な3つの支払い方法を紹介します。
窓口で現金払い
手数料なしで簡単に固定資産税の支払いを済ませたい方には、窓口での現金払いがおすすめです。納付書を用いて金融機関やコンビニなどで支払う、固定資産税の一般的な支払い方法として知られています。
窓口での現金払いは領収書をすぐに受け取れるため、支払った安心感を得られるのが大きなメリットです。納付書には期限があるため、早めに支払いましょう。
なお、コンビニでは納付書1枚あたり30万円までと上限が決まっています。30万円を超える場合は、金融機関などでの支払いが必要です。
領収書は納税証明書の取得で使用するため、大切に保管しておきましょう。
口座振替
日中忙しく窓口での支払いが難しい方には、口座振替を活用する方法が適しています。事前に口座を登録しておけば毎年自動で引き落とされるため、支払い忘れを防げます。
口座振替は、インターネットや口座振替依頼書で申請が可能です。申し込み期限は、各自治体で異なるため注意しましょう。
ちなみに東京都では、インターネット申し込みは振替当月10日まで、口座振替依頼書では振替前月10日までと定められています。
また、口座振替の場合は領収書が発行されないケースもあるため、領収書を手元に保管したい方は現金払いを検討しましょう。
インターネット支払い
インターネット支払いであれば、場所や時間に縛られず固定資産税を納税できます。インターネットを利用した代表的な固定資産税の支払い方法と、特徴・メリットは、主に以下の表のとおりです。
| 決済方法 | 特徴・メリット |
|---|---|
| クレジットカード決済 |
|
| スマートフォン決済 | QRコードを読み取り、決済アプリを利用して支払う方法 |
| Pay-easy(ペイジー)決済 |
|
固定資産税は地方税のため、以前は各自治体ごとに利用可能な支払い手段が異なっていました。しかし、近年、全国統一規格のQRコード「eL-QR」が納付書に適用され、利便性は年々向上しています。
固定資産税の減額措置
固定資産税には、住宅用地・新築住宅・住宅の再建築、リフォームなどを対象とした減額措置があります。手続きの手順や必要書類は、市区町村ごとに異なる場合がございます。上記を申告される際には、必ず市区町村へお問い合わせください。
住宅用地の特例の場合
住宅用地の税金の負担軽減を目的として設けられた措置を「固定資産税等の住宅用地特例」といいます。固定資産税の住宅用地特例の概要は、以下の表のとおりです。
| 小規模住宅用地(200㎡以下の部分) | 一般住宅用地(200㎡を超える部分) | |
|---|---|---|
| 固定資産税の課税標準 | 1/6に減額 | 1/3に減額 |
参考:国土交通省「固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置」
一戸建てだけでなく、マンションやアパートの敷地も対象となります。
新築住宅の特例の場合
新築住宅の固定資産税を一定期間減額する特例があります。新築住宅に係る税額の減額措置の概要は、以下の表のとおりです。
| 戸建て(床面積50㎡以上280㎡以下) | マンション(床面積40㎡以上280㎡以下) | |
|---|---|---|
| 固定資産税の課税標準 | 3年間1/2に減額 | 5年間1/2に減額 |
新築住宅の特例は、2026年3月31日までに新築された住宅が対象です。戸建ては4年目、マンションは6年目から固定資産税の額がもとに戻ります。
ただし認定長期優良住宅の場合は、戸建ては5年間、マンションは7年間固定資産税の特例措置の対象です。そのため、戸建ては6年目、マンションは8年目から固定資産税の額がもとに戻ります。
住宅の再建築・リフォームによる特例の場合
住宅の建て替えやリフォームにより耐震性や省エネ性能が向上したと認められた場合、固定資産税の減額措置の対象となる可能性があります。主な項目は、以下の4つです。
- 耐震リフォーム
- バリアフリーリフォーム
- 省エネリフォーム
- 長期優良住宅化リフォーム
手続きの手順や必要書類は、市区町村ごとに異なる場合がございます。上記を申告される際には、必ず市区町村へお問い合わせください。
まとめ
固定資産税は、不動産の条件により計算方法や税額が大きく変動します。
税率や評価方法を理解し、事前にシミュレーションしておくと、毎年の納税にも安心して備えられます。自宅に住宅用地の特例や新築・リフォームによる減額措置が適用されないか、今一度、確認してみましょう。
建物の火災や自然災害への備えには、JA共済の「建物更生共済 むてき プラス」がおすすめです。こちらの共済では、火災はもちろん、台風や地震などの自然災害による損害も保障されます。
また、ご契約された建物や家財について発生した火災や自然災害によって、ケガや死亡されたりしたときには、傷害共済金をお支払いします。掛捨てではないため、共済期間が満了すると満期共済金を受け取れる点も魅力です。
火災や自然災害のリスクに備えたい方は、ぜひJA共済の「建物更生共済 むてき プラス」への加入をご検討ください。
参考・出典元:
総務省 固定資産税
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_15.html
総務省 固定資産税(償却資産)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/work/shokyak_sis
大和市 償却資産の価格(評価額)と課税標準額
https://www.city.yamato.lg.jp/gyosei/soshik/49/koteishisanzei/syoukyakusisann/16072.html
主税局 税金の支払い
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/tozei_nouzei#L7
総務省 地方税統一QRコードを活用した地方税の納付の開始
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu02_02000351.html
国土交通省 固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001712029.pdf
国土交通省 新築住宅に係る税額の減額措置
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000021.html
横浜市 新築住宅に係る固定資産税の減額制度
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/y-shizei/koteishisan-toshikeikakuzei/koteishisan-toshikeikakuzei-shosai/kaoku-genmen/shinchikugengaku.html
国土交通省 認定長期優良住宅に関する特例措置
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000022.html
国土交通省 住宅リフォームにおける減税制度について
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000249.html
主税局 都税:減免・猶予等
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/work/shokyak_sis/tozei_s