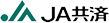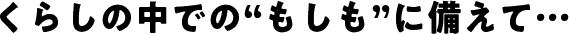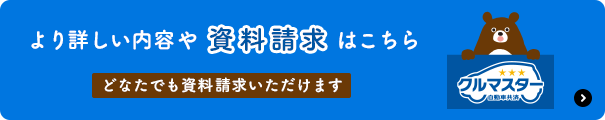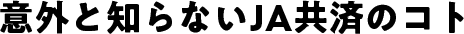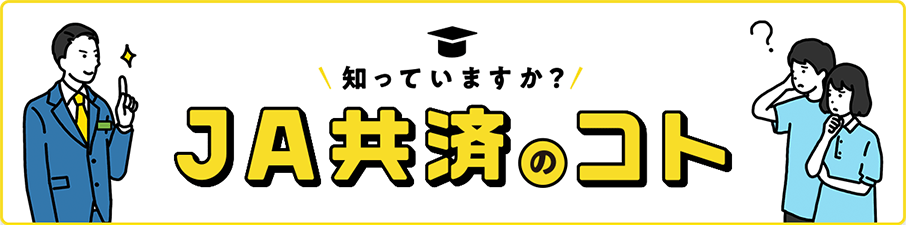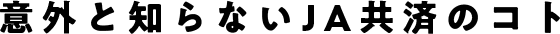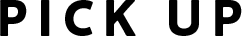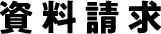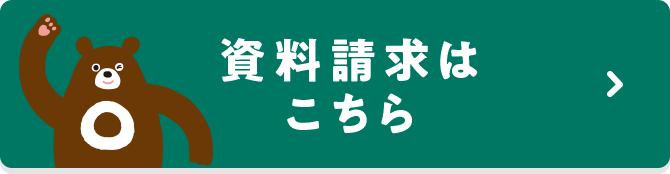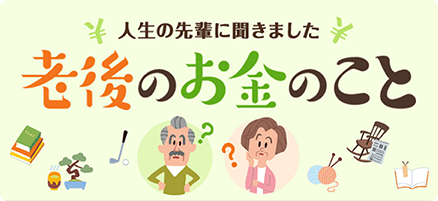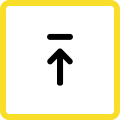車両保険には入るべきか?新車・中古車購入時の注意点も解説
“家と車”に関するねだんのこと
2025.03.31

車を購入して自動車保険を検討する際、車両保険に入るべきか迷う方もいるでしょう。車両保険に加入すると、保険料・掛金の負担は増えますが、万が一のときに車の修理費や再購入費をまかなえるメリットもあります。
例年1〜3月は、車の購入台数が増える傾向です。そこで今回は、新車や中古車の購入時に注意すべきポイントや、車両保険に入るべき理由などを解説します。車の購入や保険選びで失敗しないよう、ぜひ最後までご覧ください。
本内容は、令和7年1月の制度等に基づき、記載しています。 本記事に記載の内容・条件は保険会社によって異なる場合がございます。詳しくは保険・共済各社・各団体へお問合せください。
見出し
新車購入時の注意点
新車の購入時は、予算やオプションを十分検討することが大切です。それぞれ解説します。
無理のない予算を立てる
カーローンを組んで新車を購入する場合は、無理のない予算設定が必要です。
2023年度の「乗用車市場動向調査」によると、新車の平均保有期間は7.7年で、3割以上が10年以上の長期で保有しています。新車の購入には、まとまったお金が必要なため、返済期間5〜7年のカーローンを組んで購入するのが一般的です。
審査が厳しい銀行系ローンは金利が安く、比較的審査がスムーズなディーラー系や、信販系ローンは金利が高い傾向にあります。支払い総額を減らすには、なるべく低金利のローンを利用するのはもちろん、可能な範囲で頭金を用意するとよいでしょう。
年間のローン返済額は、年収の2〜3割までに設定すると負担を抑えられます。心配な場合は、ディーラーで見積もりを出してもらうか、無料の返済シミュレーションを利用してみてください。
オプションの必要性を検討する
新車の購入時は、オプションの見極めも重要です。
オプションには、購入時に付ける「メーカーオプション」と、納車後にディーラーで付ける「ディーラーオプション」があります。
| オプション | 装備例 |
|---|---|
| メーカーオプション |
|
| ディーラーオプション |
|
オプションを付けると、自分の好みやライフスタイルに合った車にカスタマイズできます。
ただし、ディーラーオプションはあとからでも付けられるのに対し、メーカーオプションは購入時に一緒に注文しなければなりません。自分にとって本当に必要な機能かどうか、しっかり検討しておきましょう。
中古車購入時の注意点
中古車の購入時は、走行距離や年式、車両状態、車検期間などの細かい確認が重要です。詳しく見ていきましょう。
走行距離と年式を把握する
車の状態を見るには、まず走行距離と年式を把握します。
年式が新しいのに走行距離が長すぎる中古車は、故障リスクが高くおすすめできません。
反対に、走行距離が短くても年式が古いと、放置されていた期間が長く状態が悪い恐れがあります。
1年あたりの走行距離が1万km程度であれば、適度に使われた車だと判断できます。例えば、新車登録から5年経った車の場合、走行距離が5万km前後あるかを確認するとよいでしょう。
なお、中古車市場では10万km程度までの車が一般的に流通しています。走行距離が10万kmを超えると各部品の消耗は避けられないものの、価格面では比較的抑えられるのがメリットです。定期的なメンテナンスがしっかりとおこなわれていれば、十分な選択肢となり得ます。
車両状態をチェックする
中古車の購入時は、事故や災害に巻き込まれたり、沿岸部や雪国で使われたりして、ダメージを受けた車ではないかを確認しましょう。
特に注意が必要なのは、次のような車です。
| 状態 | 問題 | |
|---|---|---|
| 事故車修理歴車 | 車のフレーム(骨格)を損傷し修理した | あとから故障しやすい |
| 水没車 | 台風や大雨で水没した |
|
| 塩害車 | 沿岸部の潮風を受けた | 金属部分が錆びやすい |
| 雪害車 | 凍結防止剤が撒かれた道路を走行した |
このような中古車は、相場よりも安い価格設定が多い傾向にあります。しかし、そもそも状態が悪かったり、あとから故障を繰り返したりして修理代が予想以上に高くなる恐れがあるため、避けるのが賢明です。
販売店によって、修理歴や状態を詳しく表示していないこともあります。必ず自分の目で車の状態をチェックし、気になることがあれば購入前に聞いておきましょう。
車検期間が残っているか確認する
費用を安く抑えたい場合は、車検期間が残っているかどうかも確認してください。
公道を走るには車検を取得している必要があります。また、車検の有効期限は新車登録時で3年、それ以降は2年ごとに更新が必要です。中古車の場合、車検期間が残っている車と車検が切れている車があるため、車検の残り期間が長いほどお得になる可能性があります。
車検が切れている中古車は、本体価格が安く設定されていますが、車検を通すための自賠責保険料や自動車重量税などの法定費用が別途かかります。そのため、車検期間が残っている車と比較する場合は、費用の総額で考えるとよいでしょう。
車の万が一に備える車両保険とは?
購入時によく注意していても、車の故障や事故が起きないとは言いきれません。そんなとき、自分の車の修理費などを補償するのが車両保険です。
車両保険を含む、車の任意保険の補償範囲一覧は以下のとおりです。
| 相手への賠償 | 人(ケガや死亡など) | 対人賠償保険 |
|---|---|---|
| 車・物 | 対物賠償責任保険 | |
| 自分への補償 | 人(ケガや死亡など) |
|
| 車・物 | 車両保険 |
車両保険は、主に次のような場面で適用されます。
- 事故で車が壊れた
- 車が水没した(地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害を除く)
- 車に落書きされた
- 車が盗まれた
- 飛び石で車に傷が付いた
日本損害保険協会の「自動車保険 都道府県別加入率」によると、2023年の車両保険加入率の全国平均は46.6%で、車に乗る方の約半数が車両保険に加入している状況です。
車の修理費用や買い替え費用は高額になりやすいため、その備えとして車両保険を利用する方が多いと考えられます。
車両保険に入るべき理由
車両保険は月々の保険料・掛金負担があることや、万が一に備える保険という性質から、加入をためらう方もいるかもしれません。ここでは、車両保険に入るべき理由を詳しく解説します。
自分の過失割合分は相手側から支払われないから
最初に覚えておきたいのが、相手側の保険による補償は、相手側の過失割合分に限られるという点です。
交通事故では負担額を公平に決めるため、自分と相手の責任を割合にした「過失割合」に応じて負担額を決めます。
例えば、過失割合が「自分:相手 = 2:8」だった場合、相手側の保険からは車の修理費用の8割までしか支払われません。自分の過失割合分である2割は自分で支払わなければならず、万が一のときに大きな負担となります。
その点、車両保険に加入していれば、自分の過失割合分は車両保険でカバーできるため安心です。
自損事故や当て逃げ事故に遭う可能性があるから
単独の自損事故を起こしたり、当て逃げ事故に遭ったりする可能性があることも、車両保険に加入すべき理由の1つです。
相手がいない・わからない事故では、相手から賠償金を受け取れません。そのような場合で、車両保険に加入していない場合、車の修理費用や再購入費用はすべて自己負担になるため、注意が必要です。
車両保険は自然災害にも対応しているから
自然災害に遭ったときにも、車両保険があると補償を受けられます。
例えば、大雨で車が水没したり、ひょう・あられで車に傷がついたりした場合は、保険金が支払われます。
ただし、地震や噴火・津波は補償の対象外ですので、ご注意ください。
車両保険が必要なのはどのような方?
車両保険が必要なのは、次に当てはまる方です。
- 運転経験が浅い方
- 車のローン返済が残っている方
- 預貯金が十分でない方
- 新車を購入し時価相当額が高い方
運転経験が浅く、運転に自信がない方も、事故のリスクを考えると車両保険への加入を検討すべきでしょう。
車のローン返済が残っている場合は、事故に遭うと修理費用や買い替え費用が重なり、経済的な負担が大きくなります。預貯金が十分でない方も、車両保険に加入しておくと万が一のときに経済的負担を軽減できるでしょう。
新車購入で車の時価相当額が高い方は、車両価値が高額なため、万が一のときに大きな費用負担が予想されます。このような場合、車両保険があれば盗難や災害、修理費用が高額だった場合でも経済的負担を大幅に軽減できることから、車両保険への加入がおすすめです。
車両保険ならJA共済のクルマスター
いくら安全運転を心がけていても、事故に遭う可能性はゼロではありません。また、当て逃げや落書き、自然災害など、予測できないトラブルで車が損傷する可能性もあります。
車の修理や買い替えには多額の費用がかかることも多く、万が一のときに手厚い保障を受けたい方は、車両保険への加入がおすすめです。
JA共済の「クルマスター」は、3つの充実保障がついた共済です。事故時の車の保障はもちろん、相手方への保障、自分と家族の保障がセットになっており、自動車事故のリスクを幅広くカバーできます。
お車の事故による賠償やご自身とご家族のケガ、修理に備えたい方は、JA共済のクルマスターへの加入を検討してみてください。詳しくは、お近くのJAにご相談いただくか、または、下記の「クルマスター」のバナーからご確認ください。
参考・出典元:
一般社団法人 日本自動車販売協会連合会 中古車統計データ
https://www.jada.or.jp/pages/114/
一般社団法人 日本自動車販売協会連合会 新車統計データ
https://www.jada.or.jp/pages/74/
JAMA 一般社団法人 2023年度乗用車市場動向調査について
https://www.jama.or.jp/release/news_release/2024/2505/
日本損害保険協会 自動車保険 都道府県別加入率
https://www.sonpo.or.jp/report/statistics/syumoku/ctuevu0000004shr-att/kanyu_jidosha_ken.pdf