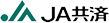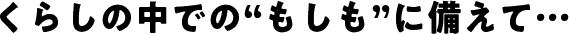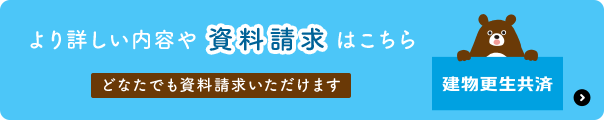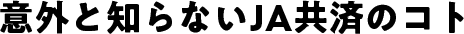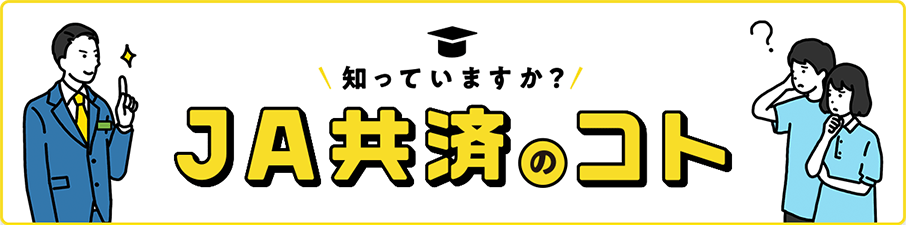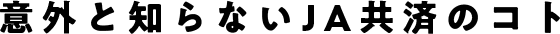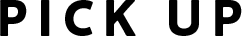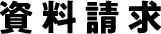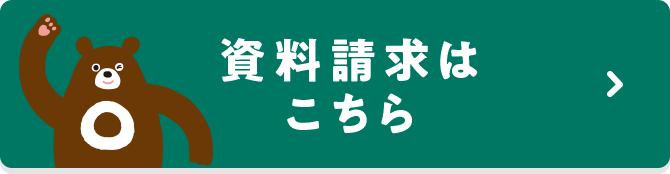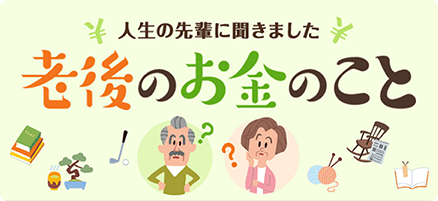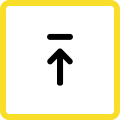火災の予防方法や家財補償が必要となる方について
“家と車”に関するねだんのこと
2025.03.31

火災保険には、建物の損害だけでなく、家財も保険(共済)の対象とする「家財補償」があります。
この補償がある保険(共済)に加入することで、家財が損害を受けた際に必要な再調達費用に備えられます。しかし、家財補償を追加すると保険料・掛金が増加するため、加入の判断に悩まれている方も少なくありません。
今回は、火災の発生原因やその予防方法、家財補償が必要な方なども紹介しているので、火災リスクや自然災害リスクに備えたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
本内容は、令和7年1月の制度等に基づき、記載しています。 本記事に記載の内容・条件は保険会社によって異なる場合がございます。詳しくは保険・共済各社・各団体へお問合せください。
見出し
火災の発生件数はどのくらい?
消防庁の発表によると、2023年の総出火件数は38,672件で、平均すると1日あたり約106件、約14分に1件のペースで火災が発生していることになります。
火災の種類ごとの発生件数は以下のとおりです。
| 火災の種類 | 発生件数 |
|---|---|
| 建物火災 | 20,974 |
| 車両火災 | 3,521 |
| 林野火災 | 1,299 |
| 船舶火災 | 58 |
| 航空機火災 | 1 |
| その他火災 | 12,819 |
引用:総務省消防庁 令和5年(1~12 月)における火災の状況(確定値)について
このように、2023年に発生した建物火災は20,974件で、全体の約54%を占めるなど、もっとも頻繁に起こる火災であることがわかります。
火災の発生原因とは?
2023年に発生した火災38,672件における、主な出火原因ごとの発生件数と割合は以下のとおりです。
| 出火原因 | 発生件数 | 割合 |
|---|---|---|
| たばこ | 3,498 | 9.0% |
| たき火 | 3,473 | 9.0% |
| コンロ | 2,838 | 7.3% |
| 放火 | 2,495 | 6.5% |
| 電気機器 | 2,205 | 5.7% |
| 火入れ | 2,175 | 5.6% |
| 放火の疑い | 1,616 | 4.2% |
| 電灯電話等の配線 | 1,520 | 3.9% |
| 配線器具 | 1,481 | 3.8% |
※発生件数1,000件以上を抜粋
引用:総務省消防庁 令和5年(1~12 月)における火災の状況(確定値)について
上記のように、2023年に発生した火災の出火原因として「たばこ」および「たき火」が特に高い割合を占めています。このような火の不始末が原因で火災が発生し、大きな被害につながることもあるため、屋内外に関わらず火を扱う際は十分な注意が必要です。
火災を予防する方法
火災はさまざまな原因で発生し、ほんの少しの油断から大きな被害につながることがあります。ここでは、火災を予防する6つの方法を紹介するので、火災を未然に防ぎたい方や被害を抑えたい方は、参考にしてください。
寝たばこをしない
寝たばこは火災の原因となるリスクが高く、避けるべき行為のひとつです。寝たばこでたばこを落としてしまったり、火種の落下に気付かず就寝したりすることで火災につながる恐れがあります。
また、たばこが原因の火災は、死者をともなう住宅火災の出火原因として多く発生しており、その危険性は極めて高いです。
例えば、飲酒後に喫煙し、そのまま眠り込んでしまうことで、火種が布団やソファに落ちてしまい、火災が発生する恐れがあります。このような危険を避けるためにも、たばこの火種が落ちても火災につながりにくい安全な場所での喫煙を心がけましょう。
また、吸い殻を灰皿に溜め込まず、喫煙後速やかに消火してから捨てることを徹底してください。これらの対策を心がけることで、たばこを原因とした火災の発生リスクを大幅に軽減できます。
コンロ使用時は火のそばを離れない
コンロによる火災の多くは、火をつけたままその場を離れたり、火をつけていることを忘れたりといった原因で発生しています。思わぬ火災を防ぐためにも、基本的に調理中はコンロのそばを離れないようにしましょう。
また、荷物の受け取りや来客対応などで、他のことに気を取られてしまう場面では、火をつけていることを忘れる危険性が高まります。コンロから離れる際は、移動前に必ず火を消す習慣を身につけておくことが重要です。
ストーブの近くに燃えやすいものを置かない
冬には暖を取るためにストーブを使用する機会がありますが、ストーブが原因となって火災が発生する可能性もあります。
ストーブが出火原因の住宅火災の多くは、可燃物の接触によって発生しているため、ストーブの近辺に燃えやすいものを置かないことが重要です。
例えば、洗濯物を早く乾かすためにストーブの近くに干している方がいるかもしれませんが、ストーブに洗濯物が落ちてしまい、そこから火災につながる危険性があります。
このように、ストーブは火災の原因となりうるという認識を持ち、安全に使用することを心がけましょう。
コンセントを掃除する
近年、配線コードなどを原因とする住宅火災は増加傾向にあります。火災を防ぐためにも、配線コードやプラグ、コンセントの定期点検や掃除をおこなうことが大切です。
配線コードなどから出火する原因としては、主に以下の3つが挙げられます。
| 出火原因 | 内容 |
|---|---|
| トラッキング現象 | コンセントに差したプラグにほこりが溜まり、湿気で電気回路が形成され、放電による火花の発生によって出火する |
| たこ足配線 | コンセントの許容量を超える電気器具をつなぎ、過負荷による加熱で出火する |
| 配線コードの劣化 | 劣化した配線コードの使用や、束ねた状態での使用で負荷がかかり、断線して出火する |
このような出火原因を取り除くためにも、以下の項目を確認しましょう。
- コンセントやプラグにほこりが付着していないか
- たこ足配線になっていないか
- 配線コードは劣化していないか
- 配線コードが家具の下敷きになっていないか
コンセントやプラグにほこりが付着している場合は速やかに取り除き、配線コードに異常が見られた場合は、新しいものに買い替えるようにしてください。日頃から対策を徹底することで、配線コードなどを原因とする火災の発生リスクの低下につながるでしょう。
住宅用火災警報器を設置して定期点検する
住宅用火災警報器は、火災発生時の被害を最小限に抑えるために、効果的な方法です。
消防庁の発表によると、2023年の住宅火災1件あたりの平均焼損床面積を比較した場合、住宅用火災警報器などの未設置住宅が22.0㎡なのに対し、設置住宅は3.3㎡と約7分の1の範囲にとどまっています。
このように、住宅用火災警報器は火災の延焼を抑える効果が期待できるため、すべての居室や台所、階段などに設置しておくと安心です。また、少なくとも半年に1回以上点検し、音声や警報音が正常に鳴るかを確認しましょう。
なお、設置後10年経過した住宅用火災警報器は、電子部品の劣化などが原因で火災を感知しなくなる恐れがあるため、新しいものに交換してください。
消火器を使えるようにしておく
火災時の延焼を抑えるためには、消火器を正しく使えるように準備しておくことが重要です。
消防庁の発表によると、2023年の住宅火災では、消火器具を使用したケースの7割以上で被害軽減効果が確認されています。しかし、消火器を正しく使えなければ、十分な効果が得られず、火災が拡大する危険性があります。
そのため、地域の防火防災訓練などに参加し、実際に消火器の使い方を学び、実践することが大切です。
また、火災はいつ発生するか予測できないため、もしもの場合に備えて自宅に消火器を用意しておく必要があります。用意した消火器は、使用期限を過ぎていないか、外観に異常がないかなどを、半年に1回を目安にチェックしましょう。
火災保険の家財補償が必要なのはどのような方?
火災保険の家財補償に加入することで、火事や自然災害による損害時に受けられる補償を手厚くできますが、そのぶん保険料・掛金も高くなります。そのため、家財補償をつけるかどうか悩まれている方も多いことでしょう。
家財補償では、火災だけでなく自然災害(地震を除く)も補償対象となります。河川の氾濫が多い地域や、台風による被害が多い地域に住んでいる方などは、加入する恩恵は大きいでしょう。
JA共済の建物更生共済なら家財に関する幅広いリスクに対応!
日頃から予防や対策をしていたとしても、火災は予期せぬ出来事がきっかけで発生するものです。また、台風や洪水などの自然災害により、自宅の家具や家電など、日常生活に欠かせないものが損害を受ける可能性があります。
これらの損害を補填するには多額の費用がかかる場合もあるため、金銭的負担を少しでも抑えたい方は、家財保障を受けられる保険(共済)への加入を検討しましょう。
火災や自然災害への備えに、JA共済の「建物更生共済 My家財 プラス」がおすすめです。こちらの共済では、火災や盗難などの事故だけでなく、台風や地震などの自然災害による損害も保障されます。
また、火災や自然災害で家財に損害が発生し、その際にケガや万一があった場合、傷害共済金を受け取れます。掛捨てではないため、共済期間が満了すると満期共済金を受け取れる点も魅力です。
火災や自然災害のリスクに備えたい方は、ぜひJA共済の「建物更生共済 My家財 プラス」への加入をご検討ください。
参考・出典元:
総務省消防庁 令和5年(1~12 月)における火災の状況(確定値)について
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/statistics/items/d0ce6161610fa99185c6f04a1ded7960c9399fb4.pdf
東京消防庁 2.寝たばこは、絶対にやめましょう。
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/kasai/10_kokoroe/chapter02.html
東京消防庁 6.コンセントの掃除を心掛けましょう。
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/kasai/10_kokoroe/chapter06.html
横浜市民共済生活協同組合 コンセント火災の怖さと、それを防ぐための予防策とは
https://www.yokohamashimin-kyosai.or.jp/useful/2018/10/electrical-outlet-fire.php
東京消防庁 7.住宅用火災警報器を全ての居室・台所・階段に設置し、定期的な作動確認をしましょう。
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/kasai/10_kokoroe/chapter07.html
東京消防庁 9.万が一に備え、消火器を設置し使い方を覚えましょう。
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/kasai/10_kokoroe/chapter09.html